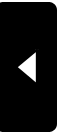【薬学生のスクラップ2021年第一期 ①】
クローン病に朗報
人工的に立体的な臓器を作り出す技術を使って、栄養分を吸収する小腸の機能を大腸に持たせることに、慶応大学のグループがねずみを使った実験で成功し、将来、小腸から栄養分を吸収できない病気の治療法につながるとして注目されている。
研究は、慶応大学の佐藤俊朗教授らのグループが行い、イギリスの科学雑誌「ネイチャー」に掲載された。
小腸は「じゅう毛」と呼ばれる突起から栄養分を吸収していて、
炎症ができるクローン病などの治療のため、
小腸を取り除くと栄養分を吸収できないため、移植などが必要になる。
研究グループでは、小腸の細胞が腸の中を流れる液の流れを感じ取ることで「じゅう毛」を作り出すことを突き止め、
ねずみを使った実験で人工的に立体的なじゅう毛を作り出すことに成功した。
そして、小腸の元となる細胞をねずみの大腸に移植したところ、
大腸の表面にじゅう毛が生え、栄養分を吸収する血管やリンパ管ができた。
ねずみは通常、小腸を取り除くと10日ほどで死ぬが、
移植したねずみでは、およそ30日間生存した。
グループでは、もともと大腸に備わっている栄養分を運ぶ仕組みを生かすことで
大腸に小腸の機能を持たせることができたとし、佐藤教授は
「すでにある臓器を必要な別の臓器に作り替えるもので、
将来的には小腸移植に変わる治療法を開発できるのではないかと期待している」と話している。
【学生の感想】
クローン病は難病指定にされている疾患で、腹痛、下痢、血便等の症状がみられる。
ほとんどの患者さんはより適切な治療をすることで、
健康な人とほぼ変わらない生活を送ることができるが
一部、小腸を取り除く必要のある人や中心静脈栄養が
肝障害によって行えなくなる人は小腸の移植が必要となる。
移植も他の臓器と比べ、複雑な免疫防御機能を持つことから
拒絶反応のコントロールが難しい。
自分の大腸に小腸の機能を持たせられることでクローン病の患者さんが
食事制限をしなくてよくなったり、移植を待つ必要がなくなるのであれば
非常によいと感じた。また、クローン病は進行する病気なので、「いつか移植するかもしれない」
と不安に思っている人にとっては、希望となるのではと考えた。
 おしまい
おしまい

クローン病に朗報
人工的に立体的な臓器を作り出す技術を使って、栄養分を吸収する小腸の機能を大腸に持たせることに、慶応大学のグループがねずみを使った実験で成功し、将来、小腸から栄養分を吸収できない病気の治療法につながるとして注目されている。
研究は、慶応大学の佐藤俊朗教授らのグループが行い、イギリスの科学雑誌「ネイチャー」に掲載された。
小腸は「じゅう毛」と呼ばれる突起から栄養分を吸収していて、
炎症ができるクローン病などの治療のため、
小腸を取り除くと栄養分を吸収できないため、移植などが必要になる。
研究グループでは、小腸の細胞が腸の中を流れる液の流れを感じ取ることで「じゅう毛」を作り出すことを突き止め、
ねずみを使った実験で人工的に立体的なじゅう毛を作り出すことに成功した。
そして、小腸の元となる細胞をねずみの大腸に移植したところ、
大腸の表面にじゅう毛が生え、栄養分を吸収する血管やリンパ管ができた。
ねずみは通常、小腸を取り除くと10日ほどで死ぬが、
移植したねずみでは、およそ30日間生存した。
グループでは、もともと大腸に備わっている栄養分を運ぶ仕組みを生かすことで
大腸に小腸の機能を持たせることができたとし、佐藤教授は
「すでにある臓器を必要な別の臓器に作り替えるもので、
将来的には小腸移植に変わる治療法を開発できるのではないかと期待している」と話している。
【学生の感想】
クローン病は難病指定にされている疾患で、腹痛、下痢、血便等の症状がみられる。
ほとんどの患者さんはより適切な治療をすることで、
健康な人とほぼ変わらない生活を送ることができるが
一部、小腸を取り除く必要のある人や中心静脈栄養が
肝障害によって行えなくなる人は小腸の移植が必要となる。
移植も他の臓器と比べ、複雑な免疫防御機能を持つことから
拒絶反応のコントロールが難しい。
自分の大腸に小腸の機能を持たせられることでクローン病の患者さんが
食事制限をしなくてよくなったり、移植を待つ必要がなくなるのであれば
非常によいと感じた。また、クローン病は進行する病気なので、「いつか移植するかもしれない」
と不安に思っている人にとっては、希望となるのではと考えた。
 おしまい
おしまい