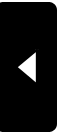「若いガン患者にこどもをもつ可能性を」(中日新聞)
日本癌治療学会は7月 若いガン患者が治療後に子どもを持つ可能性を残すための
方法を示したガイドライン(指針)をまとめました。
ガン治療を最優先しながら、これまでは説明不足だった、不妊の可能性の情報提供も行いながら
妊娠の可能性を残すための選択しを患者自らが選択できるようにした。
対応策の例は以下のようなものである。
①乳がん 手術後は速やかに抗がん剤の治療はすべきだが、開始を遅らせ卵子などの凍結保存をする
②子宮体がん がんが粘膜層にとどまっているグレード1の段階なら子宮を全摘せずにホルモン療法をする
③白血病(男性) 治療開始前、1日も早く精子の凍結保存をする
④小児がん(女子) 思春期前で排卵誘発が困難な場合などは、卵巣組織を凍結保存できる
(研究段階、一部施設のみ)
⑤小児がん 思春期以降は精子の凍結保存ができる。思春期前は現時点では方法はない。
指針では、今後緊密な医療連携が必要であるという。婦人科だけでなく、幅広いガンについて
取り扱っているのがこの指針の特長。
がん専門医と生殖医専門医が連携したシステムがある地域は全国に十数か所である。
岐阜県のガン・生殖医療ネットワークには医療機関など38か所が参加している。
病院間の垣根を越えて患者を支援する全国初の試みとして注目されている。
若年のがん患者が本人の希望に基づき、主治医らを通じて、岐阜大病院の
「がん・生殖医療外来」を受診し、妊娠機能を保持した治療に関する情報提供を受ける。
希望すると、同病院や連携先の生殖医療施設で治療を受けることができる。
不妊治療や妊娠後のサポートも受けられる。
若い患者が十分な理解の上で将来を自ら考え、選択できるための支援は必要と専門医は語る。
学生の感想

若いうちにがんがにかかった患者さんでは不妊になる可能性があると
私はあいまいな知識で知っていたが、一般的に不妊の可能性があると
知られていない気がする。
そのために、治療の後、事実を知り、ショックを受けてしまう患者さんも実際でている。
岐阜県では38の医療機関で生殖医療の連携をとっているということだがこれはもっと増えているべきと思う。
一部の医療機関だけで行っていては不十分。より多くの期間で連携を取り、少しでも今後の
少子化に向けての取り組みをすべきであると感じた。
おしまい