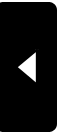「無痛分娩の医療体制構築急務」 中日新聞
お産の痛みを麻酔で和らげる無痛分娩で相次いで事故が起きている。
厚労省は研究班を発足させた。実態把握と安全に出産できる体制づくりのためだ。
妊娠中の女性にとって、無痛分娩の選択と、お産をどこで行うかの選択は待ったなし。
体制構築が急務である。
そもそも無痛分娩とは
脊髄と背骨の隙間に背中側から細い管を挿入し、
局所麻酔薬と医療用麻薬を継続的に注入する
硬膜外麻酔が一般的。
お産の痛みは脊髄が伝えるので、強い鎮痛効果が得られる。
メリットは疲労が少なく、産後の回復が早い。
デメリットは頭痛、尿が出にくくなる副作用が出やすい。
医療保険外。費用は10万円前後の追加金。
事故は、局所麻酔薬中毒や、脊髄の近くまで管が入り
「全脊髄くも膜下麻酔」の状態になったりして起こる。
事故の背景には人手が足りずに麻酔後の監視不十分であることや、
医師が合併症予防や対策に
習熟していないこと、急変時の訓練や準備不足などが挙げられる。
欧米では、無痛分娩が普及している。
施設の集約化が進み、産科の病棟には麻酔医が常駐。
しかし、国内では、分娩の半数は診療所で行われている。
麻酔医は不足している。
人手を確保するための計画分娩が行われ、陣痛促進剤を使い、
収縮が強くなりすぎることによる副作用リスクなども問題である。
お産を控えるお母さんには、「利益とリスクを考えた選択」が求められる。
学生の感想

女性にとっての出産は痛みと疲れと闘いながら大変な思いをする。
その出産に伴う痛みを麻酔により軽減もしくは無くしたりすることは
女性にとっての出産のリスクやハードルを下げる。
しかし、麻酔を扱うには多くの経験と技術が必要である。
経験不足や産科の体制が不十分のために実際、事故が起こる。
少子高齢化のためにも、出産に伴う痛みを軽減し、女性の負担を減らすことは重要だ。
今後、麻酔科医の実地経験を積める環境を作り、無痛分娩におけるリスクを軽減し
少しでも多くの女性が安心して子どもが産める環境にしてほしい。
おしまい