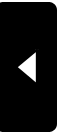『iPS細胞の研究加速!!』
体のさまざまな細胞に変化させられる人工多能性幹細胞(iPS細胞)の実用化に向けた研究が加速しています(中日新聞)
初の細胞移植が昨年、網膜の難病患者の治療で実現しました。
また、パーキンソン病患者への移植、輸血用血液の作製も臨床研究が近づいています。
今後は医療機関などに細胞を安定供給する仕組みづくりや
製薬会社を巻き込んだ創薬も動きだしています。
≪成果≫
「この5年で、さまざまな難病の人を救えると確信できるところまで来た」
京大iPS細胞研究所長の山中伸弥教授と語ります。
iPS細胞には移植後にがん化する危険性が指摘されてきたが、網膜細胞の患者さんは
移植8カ月たっても問題は起きていないそうです。
臨床応用の2例目は京大のパーキンソン病治療になりそうです。
来年の手術を目指しています。
また、京大では、血液の成分である赤血球や血小板を作製して輸血する臨床研究も来年始めるようです。
iPS細胞は無限に増やせ、高齢化社会での輸血用血液不足への切り札です。
≪課題⇒ コストと時間 ≫
実験用のiPS細胞は皮膚や血液から簡単に作れるものの、
移植する医療用の細胞は薬と同じレベルの安全性が求められます。
無菌状態の維持や安全評価に莫大な費用と時間がかかるのです。
網膜細胞移植に使った細胞は、患者の皮膚からの作製になんと、1億円以上かかり、
数カ月を要したそうです。
≪対策⇒ ストック≫
この課題を克服するのは「iPSストック」である。
iPS細胞は本来、患者自身の細胞から作るために拒絶反応が起きない、
ただ、1000人に1人の割合でいる特殊な免疫の型「HLAホモ」を持つ人の細胞は
他人にも拒絶反応が少なく、移植が可能。
この細胞をストックしておけば、必要なときにすぐ提供でき、コストも抑えられる。
iPS細胞研では、特殊な免疫の型を持つドナー探しを進めている。
≪新薬探しへの活用≫
昨年には遺伝子の異常で骨が大きくならない低身長症の患者に、
高コレステロールの治療薬スタチンが効くことが判明。
患者のiPS細胞から直接骨は作れなかったが、スタチンを振り掛けると骨になったのです。
患者の細胞を使うことで病気の状態を試験管の中で再現できる。
このことから効く薬を容易に調べられるし、動物実験でなく最初から人間の細胞で試せるのです。
今後の薬探しはアルツハイマー病などでも進んでいくようです。
iPS細胞 により 「薬探しの速度を従来の何百倍にも高められる」と山中教授は話しています。
 学生の感想
学生の感想
iPS細胞の実用化が予想以上に早く進んでいることに驚いた。
移植のコストの課題などを克服して、新薬の開発にも役立てられ、
どんどん活用されることを
期待している。
おしまい
体のさまざまな細胞に変化させられる人工多能性幹細胞(iPS細胞)の実用化に向けた研究が加速しています(中日新聞)
初の細胞移植が昨年、網膜の難病患者の治療で実現しました。
また、パーキンソン病患者への移植、輸血用血液の作製も臨床研究が近づいています。
今後は医療機関などに細胞を安定供給する仕組みづくりや
製薬会社を巻き込んだ創薬も動きだしています。
≪成果≫
「この5年で、さまざまな難病の人を救えると確信できるところまで来た」
京大iPS細胞研究所長の山中伸弥教授と語ります。
iPS細胞には移植後にがん化する危険性が指摘されてきたが、網膜細胞の患者さんは
移植8カ月たっても問題は起きていないそうです。
臨床応用の2例目は京大のパーキンソン病治療になりそうです。
来年の手術を目指しています。
また、京大では、血液の成分である赤血球や血小板を作製して輸血する臨床研究も来年始めるようです。
iPS細胞は無限に増やせ、高齢化社会での輸血用血液不足への切り札です。
≪課題⇒ コストと時間 ≫
実験用のiPS細胞は皮膚や血液から簡単に作れるものの、
移植する医療用の細胞は薬と同じレベルの安全性が求められます。
無菌状態の維持や安全評価に莫大な費用と時間がかかるのです。
網膜細胞移植に使った細胞は、患者の皮膚からの作製になんと、1億円以上かかり、
数カ月を要したそうです。
≪対策⇒ ストック≫
この課題を克服するのは「iPSストック」である。
iPS細胞は本来、患者自身の細胞から作るために拒絶反応が起きない、
ただ、1000人に1人の割合でいる特殊な免疫の型「HLAホモ」を持つ人の細胞は
他人にも拒絶反応が少なく、移植が可能。
この細胞をストックしておけば、必要なときにすぐ提供でき、コストも抑えられる。
iPS細胞研では、特殊な免疫の型を持つドナー探しを進めている。
≪新薬探しへの活用≫
昨年には遺伝子の異常で骨が大きくならない低身長症の患者に、
高コレステロールの治療薬スタチンが効くことが判明。
患者のiPS細胞から直接骨は作れなかったが、スタチンを振り掛けると骨になったのです。
患者の細胞を使うことで病気の状態を試験管の中で再現できる。
このことから効く薬を容易に調べられるし、動物実験でなく最初から人間の細胞で試せるのです。
今後の薬探しはアルツハイマー病などでも進んでいくようです。
iPS細胞 により 「薬探しの速度を従来の何百倍にも高められる」と山中教授は話しています。
 学生の感想
学生の感想
iPS細胞の実用化が予想以上に早く進んでいることに驚いた。
移植のコストの課題などを克服して、新薬の開発にも役立てられ、
どんどん活用されることを
期待している。
おしまい